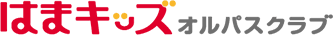【コラム】5歳児が思い通りにならないと怒るのはなぜ?理由と接し方のポイントを解説

5歳前後の子どもを育てる親によくある悩みが、「思い通りにならないとすぐ怒る」というもの。たまにならいいのですが、これが毎日続くと親もイライラが募ってしまいますよね。
どうして5歳児が怒りっぽくなってしまうのか、その理由と対策について詳しく見ていきましょう。
(1)親を悩ませる5歳児の反抗的な「怒り」
(2)5歳児が思い通りにならないと怒る理由とは
1.自己主張が強くなるが感情をコントロールしきれない
2.自分の気持ちや言いたいことがうまく言葉にできない
3.言語能力や思考力が高まって反論できるようになる
4.わがままを言って甘えている
(4)思い通りにならないと怒る5歳児への接し方のポイント
1.気持ちに共感してあげる
2.感情的にならず落ち着いて対応する
3.暴力・暴言は絶対に見過ごさない
4.長引くときは構いすぎない
5.命令ではなく提案、依頼する
6.褒めてから諭す
(1)親を悩ませる5歳児の反抗的な「怒り」
「思い通りにならないと癇癪(かんしゃく)を起こして泣き叫ぶ」
「叱ってもへ理屈をこねて口答えばかりする」
「親の注意を無視する」
「嫌なことがあるとぐずり続ける」
このような態度が続くとストレスがたまり、つい怒鳴ってしまったり、
「勝手にしなさい!」と突き放してしまったりして、自己嫌悪になる人も。
また、
「暴言をはく、たたく、蹴る、物を投げる」
というように子どもの暴言、暴力に真剣に悩んでいる場合もあります。
わが子の態度が理解できず、
「発達障害なのでは?」
「育て方が悪かったの?」
というように、不安を抱えてしまう親もいるのです。
実は、こうした5歳児の反抗的な「怒り」は特別なものではありません。誰もが通る成長過程の〝しるし〟なのです。
(2)5歳児が思い通りにならないと怒る理由とは
自己主張が強くなるが感情をコントロールしきれない
5歳ごろになると自立心が育ち、なんでも自分でやりたがるようになります。自我もはっきりしてきて、「自分はこうしたい」という自己主張が強くなってきます。一方で社会性も身についてくるので周囲の気持ちも随分と考えられるようになりますが、自分の欲望や気持ちを押さえたり、我慢したりといったコントロールは未熟な段階。
「ダメだとわかっているけど自分はこうしたい…!」
という解決できない感情により、怒ったり泣いたり、という態度を取ってしまうのです。
自分の気持ちや言いたいことがうまく言葉にできない
言語能力が高まり、大人との会話もほぼ問題なくできるようになる時期。ただ、自分の感情を具体的に話すことはまだ難しく、伝えたいことをうまく言葉にできないときも。そのもどかしさ、どうしようもない気持ちが、イライラのもととなり怒ってしまうのです。
言語能力や思考力が高まって反論できるようになる
一方で、口達者になり親の言うことに対してはなんでも口答えしてくる場合もあります。言語能力や思考力の高まりにより、言い返す力がついてきているのです。先述のとおり、自己主張が強くなっていることもあり、自分の意見を通そうとしてきます。
わがままを言って甘えている
自立心が育ってきたとはいえ、まだまだ甘えたい部分もある5歳児。親への怒りは甘えの一部とも言えます。この年齢は社会性が身についてきて、家庭の外では友だちの気持ちを思いやって遊ぶ、公共のマナーを守るなど自分なりに気を付けるようになってきます。外でがんばっている分、家では安心して甘えられる親に対してわがままを言っているのかもしれません。
(3)5歳は「中間反抗期」に差し掛かる時期
親にべったりで、言われたことに素直に従うだけだった時期は終わり、「自立に向けてのひとつのステップ」を登ろうとしているのです。
親に反抗することで少しずつ親離れしていこうとしている、ということを理解して、親も子どもへの対応を再考する必要があります。では実際にどのように接したらいいのか、次章で解説していきます。
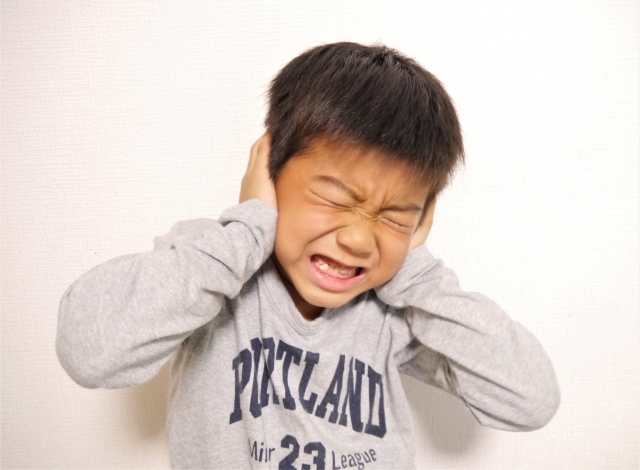
(4)思い通りにならないと怒る5歳児への接し方のポイント
子どもの発達段階を理解し、言葉にならない気持ちに寄り添い受け止めてあげることが大切です。
気持ちに共感してあげる
「~したい」「~が嫌だ」といった主張に対して親が「ダメ」「何を言っているの!」と否定から入ると、子どもの怒りはより激しくなってしまうことも。「~したかったね」「~は嫌なんだね」と共感することで、「自分の思いを理解してもらえた」と少し落ち着くことができます。
どうして怒っているのか、理由を聞くことも大切です。ただ、子ども自身がうまく言葉にできないこともあります。その場合は「どうしてなの?」と問い詰めるのではなく、「お話しできるようになったら言ってね」と声をかけ、落ち着いたときに「さっきはどうしたの?」と聞いてあげるといいでしょう。うまく言葉にできないようであれば、「~だったのかな?」と代弁してあげても構いません。
このように子どもの主張や思いを受け止めてから、できない理由や親の考えを冷静にわかりやすく伝えるようにしましょう。
感情的にならず落ち着いて対応する
子どもの怒りや口答え、ぐずりに対して、親もつい感情的になって叱ってしまうこともあるでしょう。
「こんな子はもう知らない!」
「勝手にしなさい!」
など突き放す言い方や、たたいたり放置したりという体罰を繰り返す、といった行為は子どもを恐怖で支配することになります。そうすると子どもは不安を募らせ、「自分はダメな子どもだ」と自信をなくしてしまう原因にも。
親は叱るときもなるべく落ち着くように心がけることが必要です。どうしてもイライラして子どもに当たりそうになったら、深呼吸する、別の部屋で少し落ち着くなど自分なりに工夫してみましょう。その際は、「後で話しましょう」など子どもに一言声をかけてからにするといいでしょう。
暴力・暴言は絶対に見過ごさない
ひどい言葉を繰り返し使う、人をたたく、物を壊すといった「人を傷つける」「他者に迷惑をかける」行為については、スルーしたり「仕方ない」という態度を取ったりするのはNGです。その都度「それは絶対やってはいけない」ときっちり言い聞かせましょう。家族だからと見過ごしていると、友だちにも同じようなことを言ったりしたりする可能性もあります。
ただ、必要以上に不安に思うことはありません。感情や要望をまだうまく言葉にできない5歳児においては、暴力、暴言で表現しまうのもある程度仕方がないこと。
興奮しているようであれば静かな場所に連れていく、冷たい飲み物を飲ませるなどして落ち着けるようにしてあげましょう。その上で、「どうしてそんなことをしたのか」という理由を聞いてあげてください。「今度からはたたく前にお話ししてくれるとうれしい」などと伝え、少しでもそれができたら思い切り褒めてあげるようにしましょう。
そうすれば、「暴力や暴言ではなく、きちんと言葉で伝えることがいいこと」だと、子どもも徐々に理解していきます。

長引くときは構いすぎない
いさめても理由を聞いても、怒りつづけたりぐずり続けたり、といったこともあります。「なんとか親に言うことを聞いてほしい」「親に構ってほしい」という気持ちのほか、子ども自身なかなか納得できないということもあるのでしょう。
そんなとき「いつまでぐずっているの!」と叱り続けても逆効果で、親も疲れてしまいます。逆に、子どもを黙らせたいからと親が言うことを聞いてしまうと、「怒ればいい」「ぐずり続ければなんとかなる」と間違った認識を与えることにも。
子どもの気持ちや理由を聞いて、ダメな理由を伝えたら、そのあとは怒りが長引いたとしても構わず、「ダメなものはダメ」ということを毅然とした態度で伝えましょう。ひとしきりすれば、自分自身で落ち着くことができるでしょう。
ただ、構わないといっても無視する、冷たい態度を取るということではありません。話しかけてきたらきちんと対応し、落ち着いたら声をかけて話をしてあげましょう。「あなたを見守っている」ということを伝えることが大切です。
命令ではなく提案、依頼する
自立心が育ちつつある時期なので、「~しなさい」という命令には反発を覚えてしまいます。怒りをムダにかきたてないためには、「~しようか」など提案する言い方を用いるといいでしょう。また、「~してくれる?」という依頼する言い方も、何でも自分でしたい5歳児には有効。「頼られている」「能力を認められている」と感じるとがんばってくれることも。
褒めてから諭す
怒られてばかりでは子どももおもしろくありません。それが続くと全般的に「自分はできない子」と思い込んでしまうことも。
わが子のいいところに常に目を向けて、日頃から小さなことでも褒めることを忘れてはいけません。親は大好きな親に認められたいと常に思っています。親の言葉から、どんな態度をとればいいのかを自然と判断していくでしょう。
叱るときも、褒めてから諭すように心がけてみてください。
「この間はきちんと約束が守れて偉かったね。お母さんはとても助かったよ。今日は~するのが嫌だったのかな?」
このような声がけにより「いつも自分のことを見て、認めてもらえている」と感じると、子どもの気持ちも少しは落ち着くでしょう。

(5)5歳児の子育てでは、親自身のイライラ解消も大切
イライラが爆発しそうになったら、少し子どもと離れる、違うことを考える、お茶を入れて休憩するなど、意識して落ち着くようにしてみましょう。時には外出して趣味やショッピングの時間を持つなど、自分なりのイライラ解消法を作るのもいいでしょう。
「こうした態度は一時のこと」と深刻に考えすぎず、「自立へ向けて成長しようとしている」と前向きに受け止めましょう。
(6)まとめ
一人の人として尊重し、あたたかく見守る姿勢で
今までとは違う反抗的な5歳児の態度に、はじめはとまどい悩むこともあるかもしれません。でも、怒りも口答えも成長の証し。少しずつ親から離れて、自分を確立しようとしているのです。へ理屈をこねていたとしても、一人の人間として意見に耳を傾け、向かい合うことが大切です。
ただ、まだまだ甘えたい子どもであることも事実。時にはたっぷりと甘えさせてあげることも必要です。大きな愛情を持って、その成長を見守ってあげましょう。
関連記事