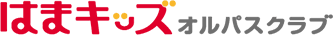【コラム】幼児期に大切な巧緻性を高める指先遊び、トレーニングとは

(1)巧緻性はなぜ重要性なの?
1.そもそも「巧緻性」とは?
2.小学校受験でも出題されている
3.巧緻性を高めるメリットとは?
(2)巧緻性を高める指先の動き
1.拇指対向により、「握る」から「つまむ」へ
2.片手での動き 「たたく」「はがす」「留める」「ひねる」
3.両手を使うことが大切
(3)巧緻性を高める5つの方法
1.折り紙
2.ぬり絵
3.切り絵、工作
4.ひも通し
5.あやとり
(4)まとめ
1.巧緻性とは?
2.巧緻性を高める指先遊び、トレーニング
3.巧緻性を身に付けるメリット
(1)巧緻性はなぜ重要性なの?
1. そもそも「巧緻性」とは?
「巧緻性(こうちせい)」という言葉を日常的に使う、という人は少ないのでは。
漢字からうかがえるとおり、「巧緻」は巧みで手のこんでいることを表します。
そこから、手先が器用なことを一般的に「巧緻性」と呼んでいるのです。
手先だけに限らず、スポーツなどにおいて「体を思い通りに巧みに動かす」といった意味を含むこともあります。
2. 小学校受験でも出題されている
「子どもの小学校受験を考えている」という親御さんは、「巧緻性」についてよくご存じかもしれませんね。
多くの有名小学校では、筆記試験・口頭試問・運動・行動観察などのほかに巧緻性を見る試験があります。
過去の一例としては、紙をハサミで切る、のりで貼る、ひもを結ぶ、お箸を使う、など。
なぜ小学校受験で巧緻性が求められるのか、その理由は次の「巧緻性を高めるメリット」を読むと理解できるでしょう。
3.巧緻性を高めるメリットとは?
巧緻性を高めることにはどういうメリットがあるのか、詳しく見ていきます。
①3つの力がアップする
指先を使うことから、まずは次の3つの力が向上すると考えられます。
・「集中力」…工作などで細かな作業を行うには、物をよく観察し指先に神経を集中させることが必要。それゆえ集中力が養われる
・「創造力」…自分の思い通りに手先が動かせるようになるということは、いろいろなものを作り出す創造力をはぐくむ
いずれも子どもに身に着けてほしい能力ですね。
②指先を使うことで脳を活性化させる
末しょう神経が集まる手のひらや指先は、脳の中の運動野・感覚野と密接につながっているとされています。
「指先は第二の脳」ともいわれ、指先を頻繁に使うことは脳の広範囲に刺激を与え、成長期の幼児の脳をより活性化していきます。
③知育や将来の学力にもつながる
何かを作ったり組み立てたりする場合、手順を考えて実行する考察力や行動力、完成形を思い描く想像力など「考える力」が養われます。
つまり、指先を使うことは生きる力をはぐくむ「知育」につながるということ。
また、過去小学生を対象に行われた研究結果によると、「巧緻性が高い子どもは、そうではない子どもと比べ指先を使う学習、繰り返し行う学習への意欲が高い」という結果も。
例えば計算で類似の問題に繰り返しトライし、わからなくても粘り強く取り組める。
つまりは、知的好奇心を持って自ら勉強し学力を伸ばしていくという、多くの有名小学校が求める児童像につながるのです。
次に、どのような指先の動きが巧緻性を高めるのかを見ていきましょう。
(2)巧緻性を高める指先の動き
1. 拇指対向により、「握る」から「つまむ」へ
まずは、0~1歳ごろの手指の発達の特徴です。
・1歳前・・・親指とそのほかの4本指が向かい合うようになり、しっかりとつかむ「拇指(ぼし)対向操作」が可能に
・1歳ごろ・・・親指と人差し指を使って物を「つまむ」こともできるように。
「握る」、「つかむ」、「つまむ」が巧緻性アップへの初歩段階となります。
2. 片手での動き 「たたく」「はがす」「留める」「ひねる」
2歳から4歳にかけては、手首や指をより柔軟に動かせるようになっていきます。
・シールを「はがす」
・クリップを「留める」
・コマの軸を「ひねる」
上記のような動きを右手や左手で行うようになり、遊びの幅もぐんと広がります。
3. 両手を使うことが大切
右手と左手をうまく連動させて使えるようになれば、より緻密な作業を行うことができるように。
①「ちぎる」「ねじる」「はめる」「通す」「はずす」
両手を使って行う動作としては、下記のようなものがあります。
・飲み物のふたを「ねじる」
・パズルを型に「はめる」
・ビーズをひもに「通す」、
・組んだブロックを「はずす」
こういった動きを、多くの子どもが4歳ごろまでに習得していきます。
②道具を使う
さらに3歳を過ぎるころには、片手に紙、片手にハサミを持って切る、など「道具を使う」こともできるようになっていきます。
4歳、5歳、6歳と年齢が上がるにつれ、使い方がより難しいおもちゃでの遊びも楽しめるようになるでしょう。

上記のような指先の動きを踏まえて、次章では巧緻性を高めるのにおすすめの遊びを5つ紹介していきます。
(3)巧緻性を高める5つの方法
1. 折り紙
小学校入学試験の巧緻性を見るテストで課題になることもある折り紙。
美しく作るには端と端をぴったり合わせて、正確に折っていく精密さが求められます。
最初は簡単な折り方から始めて、いろいろな形に挑戦してみましょう。
2. ぬり絵
ぬり絵においては、はみ出さないで慎重に塗っていく注意深さが養われます。
最初は枠内に収まらないかもしれません。どうしたらはみ出さないできれいに塗れるのか、お手本を見せてあげるといいでしょう。
色選びでは固定観念で決めつけず、子どものイマジネーションに任せてみて。絵が好きな親御さんなら、子どもの好む絵をかいてあげてもいいですね。
3. 切り絵,工作
紙を切ったり、のりで貼り合わせたりするなかで、正しい道具の使い方を習得します。
まずはケガをしないよう使い方をしっかりと教えてあげましょう。
線を引いてその上をまっすぐハサミで切れるように練習してみても。
折り紙を2つや4つに織って切り込みを入れ、展開したときの形を楽しむのもおすすめです。
4. ひも通し
ビーズなどをひもに通す遊びは集中力が身に付くほか、手の動きと視覚を上手に連動させて体を動かせるように。
小さなビーズだと難しい場合は、紙を丸めて大き目の輪っかを作るなど、ひもが通しやすいものから始めてみてください。
5. あやとり
想像力や空間認識力も養われるといわれるあやとり。両手の指をフルに活用し、さまざまな技を覚えていくことで脳が刺激されます。
また、2人で行うことでコミュニケーション力の向上も期待できるでしょう。

(4)まとめ
1. 巧緻性とは?
巧緻性とは、手先が器用であること。入学試験の科目になっている小学校もあり、幼児期に高めておきたい能力の一つです。
2. 巧緻性を高める指先遊び、トレーニング
巧緻性を高める方法としては、
・折り紙
・ぬり絵
・切り絵、工作
・ひも通し
・あやとり など。
いずれも2~4歳ごろからチャレンジできるものばかりです。
子どもの能力に合わせ、難しすぎず楽しんで取り組めるレベルのものを用意してあげましょう。
3. 巧緻性を身に付けるメリット
巧緻性が高いと、「手先の器用さ」「集中力」「創造力」がアップするとともに、指先を使うことで脳が刺激を受け活性化されます。
知育の一環にもなり、学ぶ意欲が高まることで学力の高い子どもへと成長していくのです。
小学校受験をする・しないに関わらず、幼児期に高めておきたい巧緻性。折り紙やひも通しなどはいずれも身近な道具でできる遊びなので、子どもといっしょにぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。
関連記事
カテゴリ一覧
テーマ
校舎